「…………」
ジリジリと、熱気が身体を焦がし。肌に汗が浮かんでいく。湿度の高い室内のせいで視界が歪むのを感じながら、俺はほのかに照らされた木壁をじいと見つめる。
肺に流れ込む空気の熱さに苦しさを感じながらも、俺は初めてのサウナに挑戦していた。
「……トレーナーさん。大丈夫ですか?」
こちらを伺うように、隣に座るビリーヴが俺に心配の声をかける。
「ま、まあ、なんとか。君の方は……結構余裕そうだ」
「ええ、まあ……慣れてますので」
額に汗を浮かべながらも、涼しい表情で語るビリーヴ。聞けば、サウナにはトレーニング終わりなどにたまに通っているらしい。忍耐強い彼女を思えば、なんとも納得のいく趣味である。
一方の俺はといえば、興味は以前からあったものの中々一歩を踏み出せなかったまるっきりのサウナ初心者。今回、経験者であるビリーヴに付き添って貰う形で、サウナに初挑戦したという訳だった。
「……ふ……。……ん……」
「っ……は、っ……はぁ……」
「………………」
呼吸が乱れるのをなんとか抑えつつ、サウナの空気に耐えているのだが、隣を見ればビリーヴは大粒の汗を浮かべながらも変わらず、じっとその熱気を静かに味わっていた。
「なあ、ビリーヴ、息苦しかったりしないか……? 大丈夫か……?」
「いえ……これくらいは」
思わず心配になって尋ねるが、ビリーヴは声色一つ変えることなくそう言ってのける。
「……息がつまるようなこの感覚は、トレーニングで慣れていますから」
俺の浅はかな心配の声を余所にそう言うビリーヴ。しかし、彼女の言葉ではっとさせられる。
いや、それよりも……俺は今、彼女に課してしまったあの過酷なトレーニングのその一端を、体験することができているのだ。
決してあのトレーニングは、この程度のものでは無かったと思うのだが、それでも。この程度の息苦しさで、他でも無いこの俺が折れるだなんてことはあってはいけない。ビリーヴに課してしまった苦痛は、こんな程度では無かった筈だ。だと言うのに――。
「……あの、トレーナーさん。一段下に座ってはどうですか。下の方が、苦しくありませんよ」
「あ、ああ……ありがとう……。…………いや」
ビリーヴからの気遣う言葉に感謝しながらも、自分の意思は真逆のことを考えていて。暑い空気は比重が軽く上に行くということを考えれば、彼女の言う通りに一段下に座れば楽になるのは分かる。しかし、俺には彼女があの日感じたあの息苦しさを、己に刻みつけねばなるまい。ならば、と。
「っ……!」
熱い。全身を焦がす熱気が、痛いほどに突き刺さり、灼熱が喉を焼き、呼吸はどんどんと苦しくなっていく。だが、だがしかし――。この程度で俺が、根を上げてはいけない。
「トレーナーさん。無理をしては――」
「いや……! やらせてくれ……!」「ですが……。……――」
彼女の言葉を拒否し、俺はこの苦しみの中に飛び込み続ける。心配をかけるのは心苦しいがしかし、ここで諦めてしまっては俺は己を許すことが出来ないだろう。
「…………」
チラりと、こちらの様子を伺うビリーヴ。そんな彼女に、意識を逸らさせる為にも、俺は彼女に尋ねてみる。
「……な、なあ。サウナについて、もう少し教えてくれないか? ビリーヴ」
「サウナについて、ですか?」
「ああ、その……大体、どれくらいの時間入るのが良いとかさ」
「……大体は、1セット6〜12分くらいですね」
「12分……今入ったのが5分くらいだから……あと倍くらいか」
「サウナから出たら、汗を流すためにシャワーを浴びます。それから、少しずつ慣らしながら水風呂に入ります」
「水風呂では2分ほど浸かり、それから外気浴でしばらく休憩します。そうしてまたサウナへ入り――これを2から3回ほど繰り返します。……これが、サウナの基本ですね」
「な、なるほど……」
ビリーヴの説明を聴き終え、ぼうとする頭で考える。あと6分ほどか、苦しさを感じながらもなんとか続ければ、サウナから出ることができる。そうすれば水風呂で身体を冷やし、外気で身体を休め、この熱から身体が開放されるのだろう。
ああ、ならば。サウナの魅力を感じる為にも、そしてビリーヴの経験した苦しみを少しでも自分で感じられるようにする為にも、頑張らねば――頑張って耐えねば、と……そうおもっていたのだけれど。
「っ……ふ……っあ……はっ……はっ、ぅ……」
脳が、茹で上がり。視界が眩む。心臓は嫌な音を立てて鳴り、肺は焼き付き呼吸が乱れる。
ぼうっと、歪む世界を感じながら、今何秒経ったかも分からないまま、じっと、じっと、耐える。耐えなければ――。
彼女の言葉を否定するように、俺は立ち上がりまだやれると主張をしようとした。その、筈だったのだが――。
「ぁ、あれ……?」
ぐらり。
「っ……! トレーナーさんっ!」
大きな目眩とともに、身体が崩れる。ぼやけた視界に焦りを浮かべたビリーヴの顔が映り、ああ――。
「っ……危ないっ。……出ますよ、トレーナーさん」
グッと。身体を掴まれ支えられ、ビリーヴに助けられる。そのまま、ビリーヴは俺の身体を肩で背負いながら、扉の方へと向かう。
ぶわ、と。冷えた空気が扉を開けた先にやって来る。
「……トレーナーさん、ここで休んでいてください」
彼女に連れられて、寝転がれる椅子に運ばれる。ああ、俺はなんて――。
「……今、水を取ってきます。そこでじっとしていてください」
そう言って外へと向かうビリーヴを虚ろな頭で眺める。ああ、やってしまった。苦しさに耐えることができず、こともあろうに担当に、ビリーヴに迷惑をかけてしまった。俺はなんて駄目なトレーナーだろうか。
「これを飲んでください。少しでも水分を補給しましょう」
キャップを緩めペットボトルをこちらの口元まで運び、俺の頭をそっと持ち上げるビリーヴ。なんとか口を開くと、冷たい水が入ってきて喉を潤す。
「あ、ありがとう……ビリーヴ……」
「……僕は、汗を流してきます。しばらくトレーナーさんは、そこで休んでいてください」
持ってきたペットボトルを俺の顔のすぐ横に置くと、ビリーヴはこちらに背を向けシャワーの方へと向かっていった。
外気が内の熱を冷まし、未だ抜けきってはいないぼんやりとした頭でビリーヴを眺める。
水着姿で、シャワーを浴びるビリーヴ……。彼女の薄く、華奢な身体を見て、思う。
俺は、あの子にどれだけの負荷を掛けさせてしまったのか、と。
目に焼き付いて離れない、あの地獄のような夏合宿の時のビリーヴのマスク姿。呼吸もままならず、何度もむせ、苦しみ、藻掻いていたあの姿は、どうしたって、一時たりとも忘れられない。
彼女に大きな負担を掛けさせ、苦しませたこの責任は、自分自身にある。
今日、少しでも息ができないことの苦しみを実感できたからこそ思う。俺は、彼女にとんでもないことを強いてしまったのだと。忘れたことは無い。しかし、より強烈に、今の俺の心にはその事実が、刻まれているのだ。
――――
「……トレーナーさん」
しばらくして、ビリーヴが戻ってきた。
「気分は、どうですか?」「……うん、良くなったと思う」
まだあまり回っていない頭でそう応える。
「……いえ、気分は悪そうですね。……それも、体調だけではなくメンタルの方も」
「……なんで、分かるんだ……?」「……。顔に、出てますから。全部」
ふう、と溜息を一つ吐いて。ビリーヴは俺の横に座る。
「……すまん、ビリーヴ」「いえ、僕ももっとちゃんと止めれば良かった。……どうして、こんな無理をされたのですか?」
その言葉には言外に、普通ならそんな無茶はしないだろう、何故そのようなことをしたのか、と。問いただすような意図が現れていた。
「……息、苦しくて。ああ、きっとビリーヴは、こんな苦しみを味わったんだろう、って思ったら……」「…………なるほど」
言葉の数は少なかった。しかし、それでも彼女は理解をしたのだろう。一言、そう言うと、彼女は黙りこくってしまった。
「…………」「………………」
「――トレーナーさん」
不意に、ビリーヴが口を開く。
「僕は、あのトレーニングのことを、忘れたことはありません」「っ」
「苦しかった、辛かった。あの息苦しさを、……忘れたことはありません」
「ビリーヴ……俺は――」「――僕は、速くなれました」
俺の言葉を遮って、ビリーヴは言う。
「あのセントウルステークスで、スプリンターズステークスで。僕が一着になれたのは、あのトレーニングのお陰です」
「僕は、自分の走りの限界を感じていた。完璧な仕事ができたと思っていたからこそ、これ以上なんて、無いと思った。……だけど、それを貴方は打ち壊したんです」
「ビリーヴ――」
「――僕は、“速く"なれました」
「っ……!」
「貴方のお陰です。貴方のお陰で、あの低酸素トレーニングがあったから、僕は速くなれた。完璧な仕事が、できるようになった」
「だから……あのトレーニングも、僕は誇りに思っています。あれも立派な、“仕事"だった。僕の、そして貴方の――。……なので、誇ってください。トレーナーさんも、あの“仕事"を、ちゃんと」
ビリーヴの言葉には、揺るぎの無い、彼女の信念が、詰まっていた。それが、分かってしまった。自分には……。
だから、俺は――。
「……すまん、ビリーヴ。君の言う通りだ。あれは……俺の、仕事だった。責任は、俺にある。そして、その仕事の成果も、ちゃんと――。だから、逃げない。自分のやった仕事から、俺はもう逃げない」
「……はい。……ありがとうございます」
「いや、こちらこそ、ありがとう。それから、ごめん。色々迷惑かけて」
ビリーヴの方を向くと、丁度。ビリーヴと目が合った。ビリーヴは、少し困ったように、そっと優しく微笑む。
「……ああ、そうだな。頭も、スッキリした気がするよ」
「そうですか。……よかった」
思い出したように、水をこくりと飲む。調子もだいぶ良くなった。これなら、またサウナに――。
「……トレーナーさん。またサウナに入ろうとしていますか?」
「……なんで分かるの」
「……顔に、書いてありますから」
静かに、ビリーヴに釘を刺されてしまう。いや、しかし……折角俺に付き合って貰ったのに迷惑を掛けて、その上こんなすぐに終わらせてしまうのはどうしても偲びない――。
「僕のことは、良いですから。……それより、着替えて少し休憩したら食堂に行きましょう。サウナの後のご飯も、良いですよ」
「……! そう、なのか?」
「わ、わかった」
二度目の釘を刺され、思わず頷く。芯の強い彼女の言葉には、どこか有無を言わさない強さがあった。
「……でも、楽しみだな。サウナ飯。どんなものがあるんだろう」
「……おすすめ、教えます」
「え、本当か……!? ありがとうビリーヴ!」
「それじゃあ、もう少し。ゆっくりしましょう。サウナ飯も、逃げはしませんから」
「ああ……!」
そうして、俺たちは火照った身体をゆっくりと外気で冷ます為、まだ見ぬサウナ飯に期待を膨らませながら、ゆっくりとじっくりと、穏やかな時間を過ごすのであった。
サウナが似合いそうな2人
そういや家族風呂ならぬ家族サウナとかもあるとこにはあんのかな




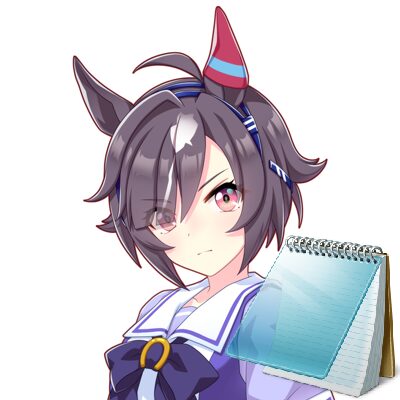

![商品名:ウマ娘 シンデレラグレイ 21 [ 久住太陽 ] 《2025/09/19発売》](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/457cba7f.9a1b8300.457cba80.2f0a127c/?me_id=1278256&item_id=25238659&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8160%2F2000018288160.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext?giaid=96646)