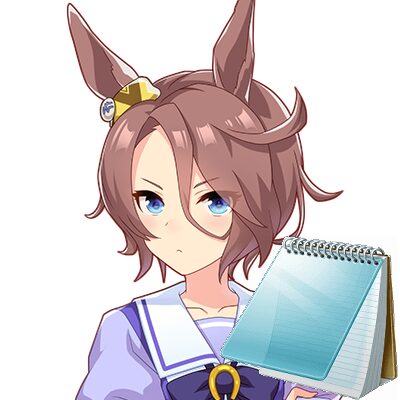無音の部屋の賑やかしに点けたテレビから流れ出した音で、ああ、今年もそんな季節かと今更のように思い出す。去年自分が走って優勝したレースに随分な言い草だとは思うが、それを一時忘れてしまうほど、去年までの数年と今年の一年は違っていたのだ。
志望理由書の中でしか使えない言葉遣いを随分覚えた。爪の先ほどの油汚れを気にする神経質な主婦のように、苦手な科目の間違えた問題を何度も解いた。やっている間は世界で一番退屈な作業だと思っていたし、もう一度やれと言われたら一目散に逃げ出そうと思うけれど、終わってしまえば何故か少し寂しい。今までの苦労を合格の通知ひとつで忘れてしまうのだから、アタシもとんだ現金な人間だったということに今更のように気付かされて、ほんの少し苦笑してしまった。
勝てば天に上るほど嬉しくて、負けたら死にたくなるほど悔しい。限りなく単純で限りなく大きなレースの世界から一度身を引いて、有意義だけれど無味乾燥な作業に一年間浸るというのは、アタシの中に随分と違う感覚を作っていったような気がする。
志望校に受かったことをあいつに伝えに行くときは、合格発表を見るときよりも気持ちが動いた。レースで勝ったときと同じくらい嬉しくて、誇らしくて。
でも、アタシの合格をアタシが思っていた以上に、自分のことのように喜んでくれたあいつを見ると、今まで忘れようとしていたことを嫌でも自覚して、少し寂しくなった。
来年の春には卒業する。もう次の進路も決まった。
だからもう、トレーナーと担当じゃなくなる。
あんたのおかげで、走ることにけじめをつけられた。だから今度はちゃんと、自分がどう生きるのかを自分で決めたい。
引退を決めた一年前のアタシが、この言葉をあいつに伝えるために、どれだけの勇気が必要だったかは、アタシしか知らなくてもいいことだ。
タイシンがどんな選択をしても俺はタイシンを応援してる、と言ってくれたあいつの言葉はあまりにも想像通りすぎて、少し笑ってしまったけれど。
でも、伝えたかったもうひとつのことは、結局言えずにここまできた。
──今日はきっと、その日になるだろうか。
コートを着て寒空の下に出たあとでも、そんなことをずっと考えていた。
今日はただ、あいつと待ち合わせをしているだけだ。どこに行くかは決めていない。
いや、行きたい場所はあった。約束をしただけで胸がいっぱいになって、あいつが行き先を聞かないのをいいことに、今までずっと言い出せないでいた。
逃げ道が欲しかった。ただあいつに会って、一緒に食事をして、彩りを増した街を見ながら、今までと同じように話をする。アタシとあいつがこれからどうなるのかも、どうなりたいのかも、言わずに済む。
今まで随分迷惑をかけてきたと思う。あいつがそんなことを気にする奴じゃないことはよくわかっているはずなのに、気がつけばそんなことばかり考えている。
──やっぱり、怖い。
自分の気持ちを、言葉にして伝えるのは。
「ごめんな。寒かったろ。
ちょっと仕事が長引いてさ。待たせちゃったな」
少し頬の赤くなった顔を見ると、怒るよりもずっと、心配と安心が押し寄せてくる。
「知ってる。
だから急いで来たんでしょ。手袋も忘れるくらい」
きっと違う理由で赤くなった指先も、全部わかってしまうくらいに。
「…バレたか。
でも、走ってたらどうでもよくなっちゃってさ」
いつもそう。そうやって、寒いのも痛いのも何も知らないみたいに、無邪気に笑って。
でも、そんな子供みたいな笑顔の中に、何かに思いを馳せるように目を細めて、優しく穏やかに微笑む顔があるのを、アタシは知ってる。
「ありがとうな。こんなに寒いのに」
誰かのことを思って笑うときのそんな笑顔が、どうしようもなく好きだった。
「いいの。
…待っててあげたかったから。あんたのこと」
やっぱり、アタシは諦めたくない。あんたのこと。
あんたの顔を見て、心からそう思った。
「…そっか。ありがとう。
とりあえず店入ろうか。寒いだろ」
だから、あんたの袖を摘んで引き止めるのも、もう躊躇わない。
「…その前に、ちょっと行きたいとこあるんだ。
…ついてきてくれる?」
分かりやすい派手さはなく、周りに店があるわけでもないからか、ロープウェイを使わなければ来られないような場所だからか、人が疎らで静かなことも、アタシの性に合っていた。
これからすることを思うと、去年とちっとも変わらない景色があることに、それだけで安心する。
「…小学校の4年生くらいまで。
気づいたきっかけが可笑しくてさ。貰ったおもちゃの返品保証書が近所のデパートのやつだったんだ。小学校の卒業までは騙したかったんだけどなって親が言っててさ。慣れない英語で手紙まで書いて。また笑っちゃった」
「なにそれ、ふふっ…!
…あんたの親御さん面白いね、あんたと同じ」
やっぱりあいつは、ちゃんと楽しい思い出の中で生きてきたんだ。そうでなければ、あんなに人に優しくなれるはずがない。
それだけははっきりわかる。
「…アタシは、信じてなかった。はじめから」
アタシは、そうじゃなかったから。
…レースに負けて、虐められて塞ぎ込んでたときに母さんがここに連れてきてくれて、きっとサンタさんがプレゼントをくれるって言った」
店を切り盛りしなければならない母にとっては、クリスマスのこの時期がどれほど大切なものだったのか、今のアタシは知っている。けして多くはない売り上げをなんとかやりくりして、プレゼントを用意してくれていたことも。
「でも、アタシはサンタなんていないって言った。
…もしいるなら、アタシがいつまでも馬鹿にされてばっかりなのは、悪い子だから助けてもらえないからなのって。
…ひどいよね。アタシのこと励ましてくれてたのに」
あの頃のアタシは、人の善意を信じることは悪だと思っていた。
アタシの周りは悪意に満ちた人間ばかりで、まともな奴はひとりもいない。
そんなのは嘘だとわかっている。彼らはただの、どこにでもいる子供だったのだ。
だからこそ、そのただのどこにでもいる人間が、下に見た相手がいるというだけであんなにも残酷になれるのに、誰かを信じるとか助けるとか口にするのは、現実を知らない偽善としかアタシには思えなかった。
そう片付けてしまうのは都合がよかったのだ。あの頃のアタシは本心からそう思っていて、それがただの傲慢だと言っても、きっと受け入れられなかっただろうけど。
「タイシンが辛い思いをずっとしてきたんだって、わかってくれてるよ。タイシンのお母さんも」
母を偽善者と呼んだと思いながら生きていくことの意味なんて、何も知らなかったんだから。
その人がどんな思いでアタシに手を差し伸べてくれたのか、知りもしないで。
「…そうだね。でも、母さんだって辛かったんだ。アタシの身体が小さいのは自分のせいなんだって、ずっと思いながら生きてた。
それでも、アタシのことずっと心配してくれてた。
でも、アタシは辛いのは自分だけだって思ってた。他人の気持ちなんて意味ない、何の助けにもならないんだって」
気持ちだけでなんとかなるなら、アタシはこんなに苦しんでない。
他人がしてくれるのは同情だけだ。だから、自分を救えるのは自分しかいない。
勝手にそう決めつけて、誰かの優しさを受け止められない、弱い自分の言い訳にしていた。
誰も愛せない。誰も信じられない。
そういうふうに自分で自分を貶めてきたことに気がついたときから、もう誰の顔もまともに見られなくなった。
「次の年から、ひとりでここに来るようになった。
でも、ツリーを見るたびに、あのときのこと思い出してさ。辛くなってすぐ帰った。
…でも、夜景の光はそんなこと知らないみたいに、いつだって綺麗で」
自分を貶す誰かを憎み続けて残ったものは、哀れなほど薄っぺらな心と、それで誰かを傷つけてきた自分の罪だけだった。
ここにひとりで来なければならなくなったときから、その罪と向き合わなければならなくなった。それが耐えられなくて、ずっと逃げていた。
なのにこの景色は、アタシが好きだったころのまま、いつまでも美しいままだった。
「好きだったんだ。ここに来るの。本当に綺麗で、ずっと見ていたくて。
でも、アタシはいっつも、ここに来たら嫌なことばっかり思い出してさ。
…なんか、自分の思い出を自分で汚してるみたいで、切なくて」
でも、あんたがいたから気づけたんだ。泥にまみれても、アタシには大切な思い出があったんだって。
「…だから、あんたと来たかったの。
あんたが一緒にいてくれたら、ここが好きだって、またちゃんと思える気がするから」
あんたと会って、もう一度世界が色づいて見えるようになった。
だから今日は、前を向く日にしたい。
今までずっと向き合えなかったものを、ちゃんと好きって言ってあげられる日にしたい。
この日が来たら思い出す。
アタシはちゃんと、生きていたいって思えるようになったんだって。
あんたがずっと支えてくれたから、アタシはアタシでいることを、許してあげられたんだって。
こんなアタシにも掴めるものがあるって、教えてくれて」
あんたが勇気をくれたから、ちょっとだけ昔の自分とも向き合える気がする。
「…俺の力じゃない。タイシンが前に進めたのは、タイシンが頑張ったからだよ。
それは誰にも偽れないし、嘘だとも言わせない」
あんたがくれた思いに応えられたから、アタシもちゃんと誰かを信じられるんだって、気づけた。
「それでも、だよ。アタシは走れるんだって、気づかせてくれたのはあんたじゃん。
…だから、心から思うよ。あんたがアタシのトレーナーで、本当によかった」
やっぱり自分のことは、まだ時々好きになれないままだけれど。
「どっかの誰かが、好き好きうっさいからさ。
…だから、アタシもちょっとだけ、アタシのこと好きになれるように頑張ってみる」
そう思いながら前に進んでもいいんだって、あんたは言ってくれたから。
「大丈夫か!?」
でも、そんなアタシを律儀に心配してくれるあいつの顔を見ていたら、いつの間にか微笑んでいた。
「…言った。あははっ。言っちゃった。
怖かったんだ。怖くて、言い出せなかった。昔の弱いアタシのことも、今はもうひとりで立てるってことも。
そうしたら、もう一緒にいてくれなくなっちゃうのかなって」
ああ、やっぱりそうだ。
アタシ、本当にあんたが好きなんだ。
「でも、ちゃんと伝えたかった。伝えなきゃいけないって思った。あんたがいてくれたから、アタシは変われたんだって」
でも、だからこそ、言わなくちゃ。
これがあんたのしてくれたことの証なんだから。
「あんたがいなくても、もうアタシは大丈夫」
なら、アタシがひとりで立てるようになったら、あんたはいなくなっちゃうのかなって、ずっと怖かったんだ。
でも、アタシはあんたのそばにいたい。
寄りかかるためじゃなくて、一緒に生きていたい。
あんたはあんたでいていいんだって伝えられるような、あたりまえの幸せをあげたい。
あんたがアタシに、そうしてくれたように。
「だから、いてくれる、じゃなくてさ。
…アタシのためじゃなくて、あんたがそうしたいんだって、言って。
一緒にいたいって、言って」
あんたと一緒に歩いてきた、アタシのままでいたいから。
あんたがそう言ってくれたら、これからもずっと、そんなアタシでいられる気がするから。
もう俺、きっと離せないぞ。タイシンのこと」
「いいって言ってるじゃん。
…そうしたい。そうしてほしい」
もう、何も言わなくてもわかった。
抱きしめてくれた温度が、何もかも教えてくれた。
これが、大好きってことなんだって。
冷えてるでしょ」
二人並んで歩く帰り道を、手を繋いでゆっくりと辿る。
アタシと全然違う、大きくて逞しい手。
あのときは意地を張って握れなかったけど、今ならその大きさがよくわかる。
それがずっと、アタシを守ってくれたんだってことも。
信じて、待ってる。
どんな言葉よりもその心に救われたか、きっとあんたは知らないんだろうけど。
アタシはずっと覚えていたい。この大きな手の中に、あたたかい温もりがあったんだってことを。
あんたのこと、大好きだって。
時間をかけてゆっくり一歩半の距離を埋めていく二人が見たいだけの人生だった
いっぱい幸せになれ…
手を繋いでいたらタイトレ君の指で掌に「すき」と書かれて真っ赤になるタイシンだ
ちがった
よかった
明日会えたらそのときは 素直になれたらいいな